木々が葉を落とし、朝の空気に冷たさを感じる今日この頃。
11月上旬のこの時期は、二十四節気では「立冬(りっとう)」と呼ばれ、暦の上では冬の始まりを迎えます。
立冬って何?自然界が教えてくれること
立冬は「冬が立つ」と書くように、本格的な冬の入り口を示す大切な節気です。
太陽の陽気が少しずつ隠れ始め、自然界のすべてが「休む」「蓄える」モードに切り替わる時期。木々は葉を落として栄養を根に蓄え、動物たちは冬眠の準備を始めます。
私たち人間も、この自然のリズムに従うことが、冬を元気に乗り切る秘訣なのです。
この時期、
「手足が冷える」
「関節が痛む」
「なんとなく気力が出ない」
「風邪をひきやすい」
といった症状はありませんか?
これらは体が「冬モード」に切り替わろうとしているサインです。
特に40代以降の女性は、更年期による体の変化と冬の寒さが重なり、冷えや疲労感を強く感じやすい時期。でも、正しいケアを知っていれば大丈夫。冬は恐れる季節ではなく、自分の体としっかり向き合える大切な季節なのです。
東洋医学が教える立冬の体質変化
「腎」の季節がやってきた
東洋医学では、冬は「腎(じん)」の季節とされています。
腎は生命力の源であり、成長・発育・生殖、そして老化とも深く関わる重要な臓腑です。現代医学の腎臓とは少し意味が異なり、もっと広く「生命エネルギーの貯蔵庫」と考えてください。
腎には先天的に親から受け継いだエネルギー(先天の精)と、日々の生活で補充するエネルギー(後天の精)が蓄えられています。冬は、このエネルギーを消耗せず、しっかりと蓄える季節なのです。
「寒邪」という見えない敵
冬に注意すべきは「寒邪(かんじゃ)」という邪気。
寒さは体の表面だけでなく、深部まで侵入し、血液の流れを滞らせ、痛みや冷えを引き起こします。
寒邪の特徴は:
- 体を収縮させ、気血の巡りを悪くする
- 関節や筋肉に痛みを生じさせる
- 下半身、特に腰や膝を冷やしやすい
- 女性特有の不調(生理痛、生理不順)を悪化させる
この時期は、手首・足首・首元は温めたい時期!
そこから邪気が入ると考えられているので、なるべく襟元が詰まった洋服をお選びくださいね。
陽気を守り、陰を養う冬の知恵
冬は「陽気を閉蔵する」季節。
つまり、体の温かいエネルギーを外に漏らさず、内側にしっかりと保つことが大切です。同時に、静かに「陰」を養うことで、春に向けて新しい命を芽吹かせる準備をします。
なので忙しい時期ですが、お休みの時間を意識的にとることが養生になります。
更年期世代と冬の深い関係
40代以降の女性は、東洋医学でいう「腎の衰え」が始まる時期。
これは自然な老化現象で、更年期の症状とも重なります。
腎が弱ると:
- 冷えを感じやすくなる
- 腰や膝が弱くなる
- 疲れやすく、回復に時間がかかる
- 夜間の頻尿が増える
- 不安や恐れを感じやすくなる
だからこそ、この季節に腎をしっかりケアすることが、これからの人生を健やかに過ごすための鍵となるのです。
経絡・ツボで冬支度〜体を温める特効穴
腎経のケアで生命力アップ
湧泉(ゆうせん):足裏の土踏まずの中心よりやや上、指を曲げるとくぼむところ
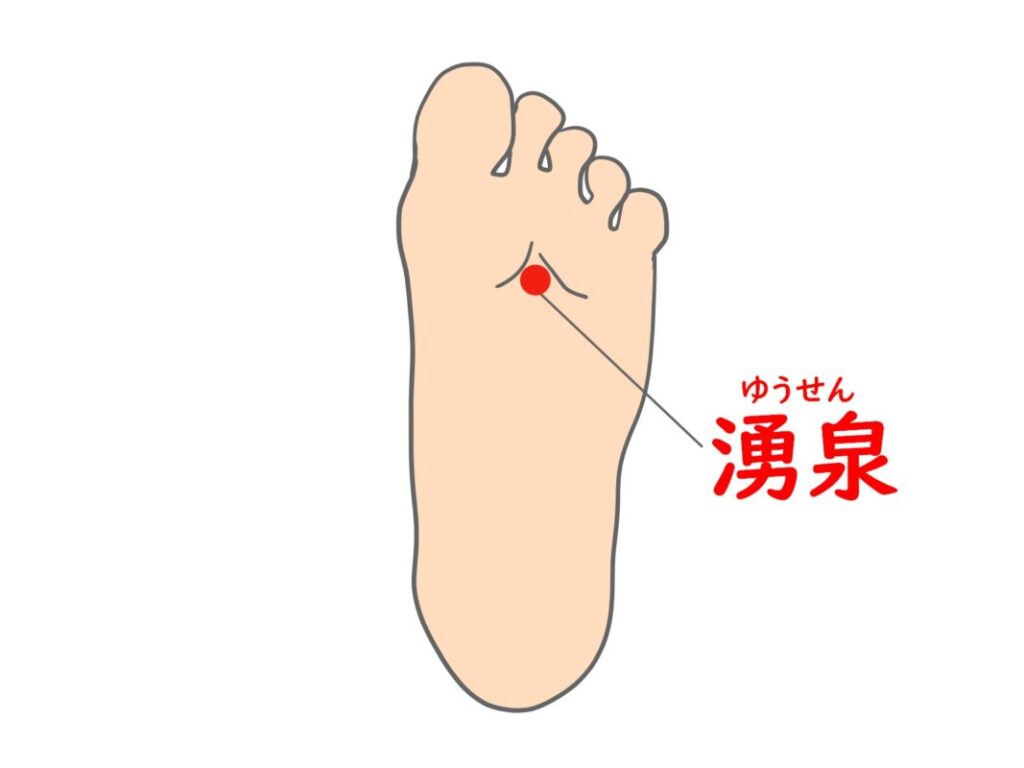
- 腎経の第一穴で、生命力が湧き出る重要なツボ
- 両手の親指を重ねて、グッと押し込むように刺激
- 就寝前に3分間押すと、冷えた足先が温まり眠りやすくなります
- ゴルフボールを踏みながらテレビを見るのも効果的
太渓(たいけい):内くるぶしとアキレス腱の間のくぼみ
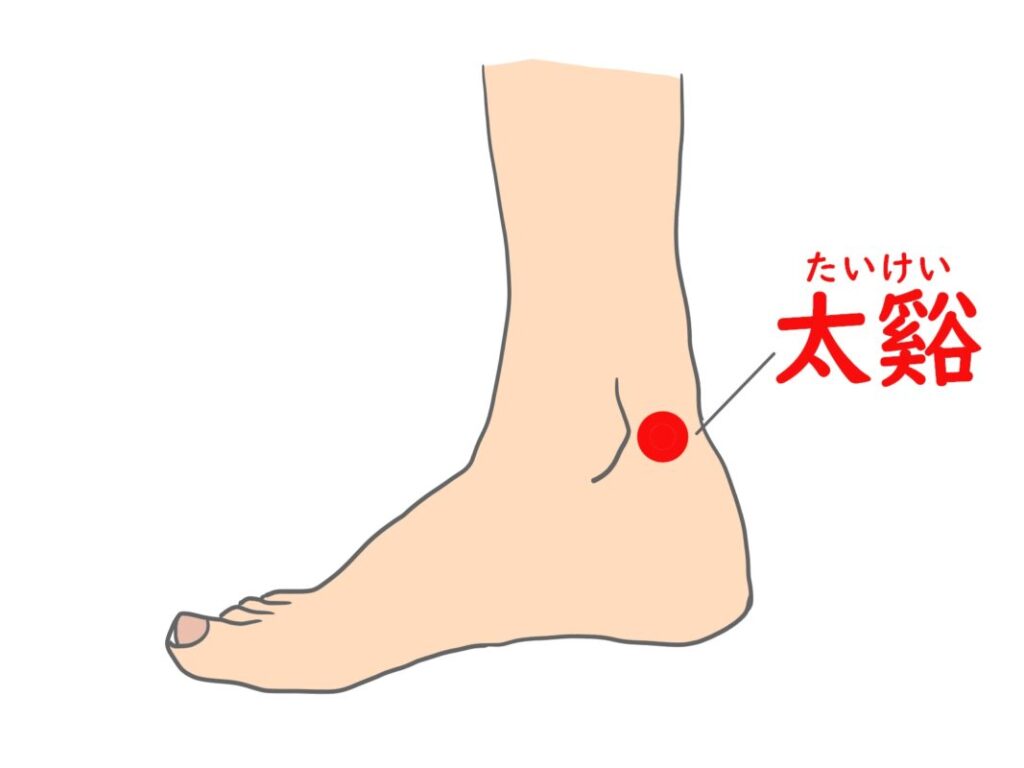
- 腎経の原穴で、腎の根本的な力を高める
- 両手の親指でゆっくりと円を描くように刺激
- 慢性的な疲労や腰痛にも効果的
- お風呂上がりの温かいうちに押すとより効果的
膀胱経で背中の冷え対策
腎とセットで考えられるのが膀胱経なので、そこに対応するツボを押すのもおすすめ!
腎兪(じんゆ):腰に手を当てたとき、親指が当たるあたり(第2腰椎の両脇)
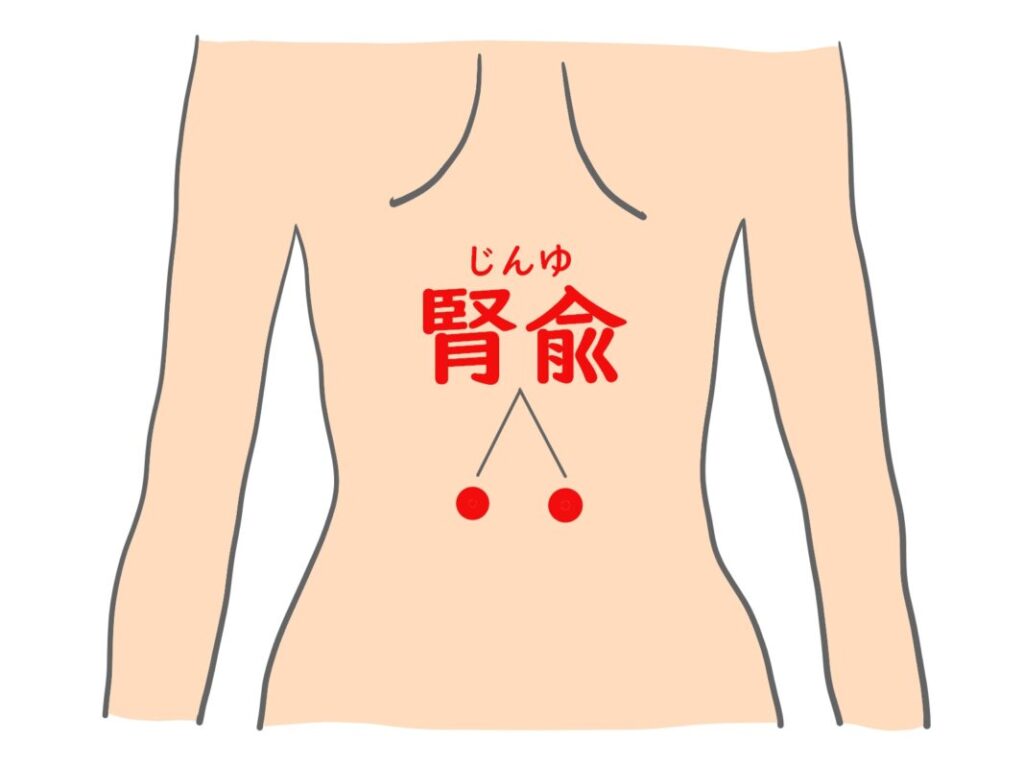
- 腎を直接温め、元気にする重要なツボ
- 指で押すよりも、カイロやせんねん灸で温めるのがおすすめ
- 腰痛、生理痛、頻尿にも効果的
命門(めいもん):腎兪の真ん中、背骨の上(おへその真裏)
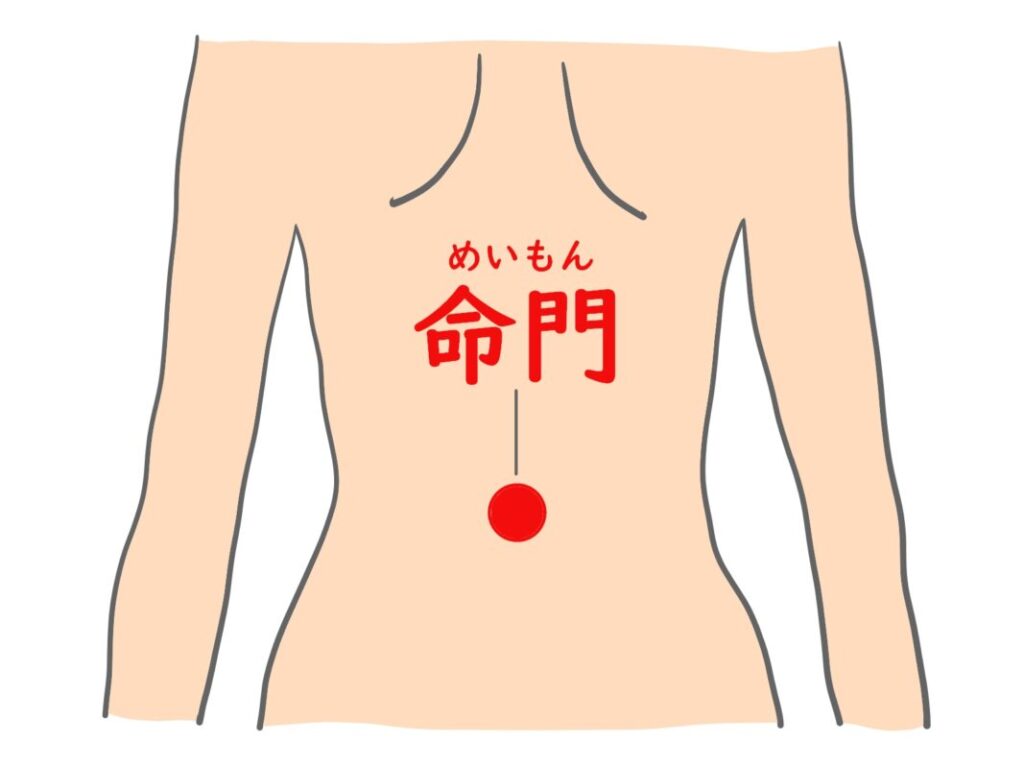
- 「命の門」という名の通り、生命力の源
- カイロを貼る特等席!
- 下半身全体の冷えを改善
女性の味方「三陰交」
三陰交(さんいんこう):内くるぶしから指4本分上、骨の後ろ側
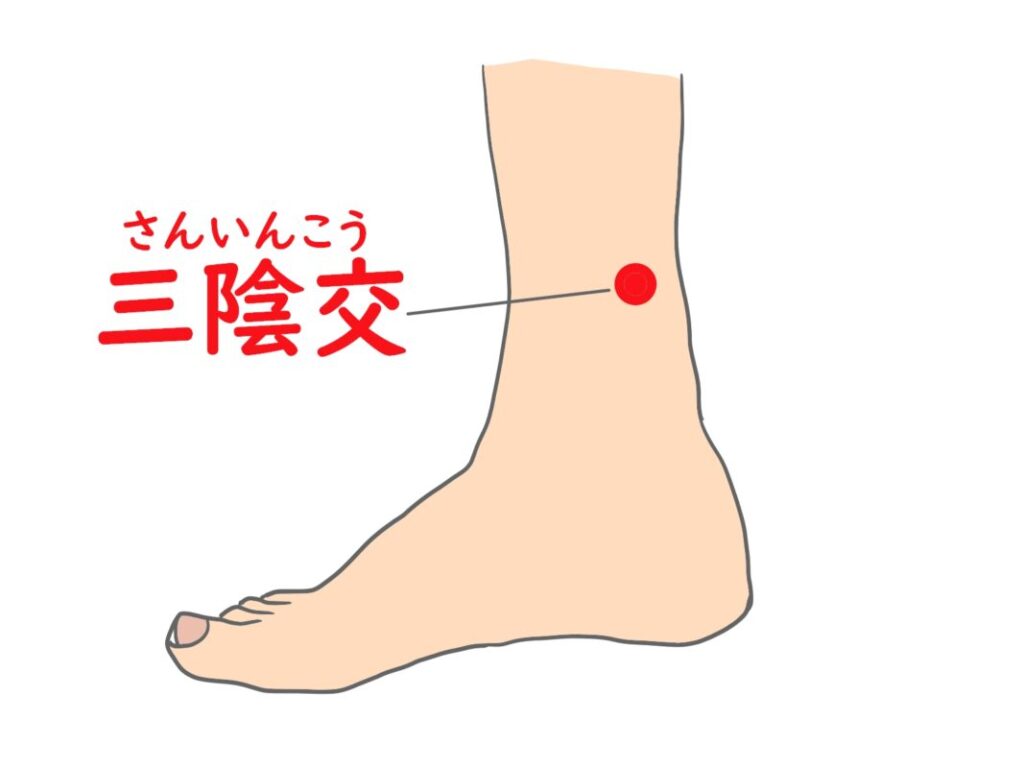
- 肝・脾・腎の3つの陰経が交わる万能ツボ
- 冷え性、生理痛、むくみ、更年期症状に
- 両手で足首を包むようにして、親指でじっくり押す
- レッグウォーマーで温めながら過ごすのもおすすめ
下腹部を温める特効穴
気海(きかい):おへそから指2本分下
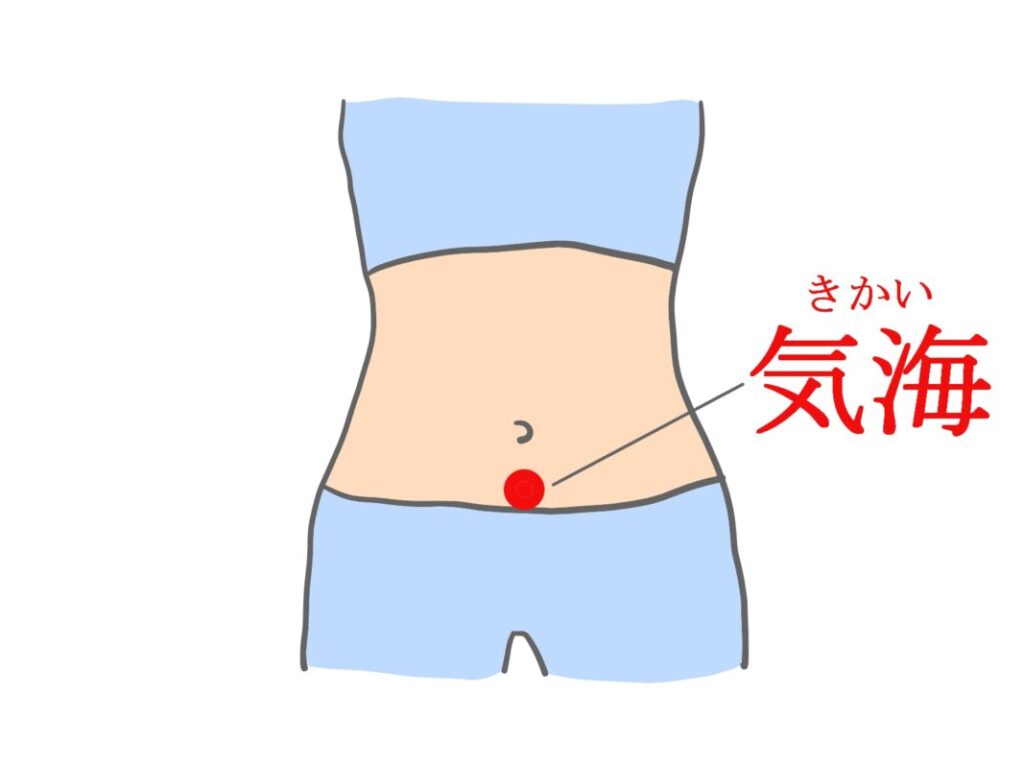
- 気のエネルギーが集まる海
- 疲労回復、冷え性、婦人科系の不調に
関元(かんげん):おへそから指4本分下
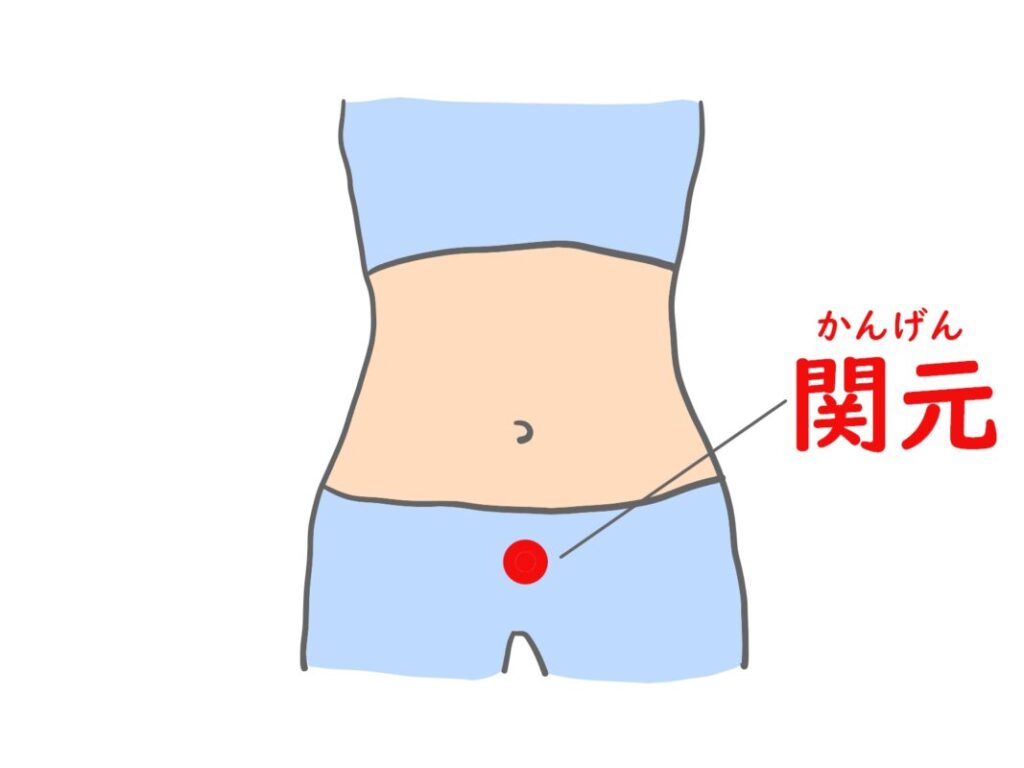
- 元気の関所、生命力の貯蔵庫
- 両手を重ねて、ゆっくりと息を吐きながら優しく押す
- 腹巻きにカイロを入れて、このツボを温めるのが冬の最強養生法
食事で内側から温める〜冬の薬膳
黒い食材で腎を補う
東洋医学では「黒い食材は腎を養う」とされています。冬は積極的に黒色の食材を食卓に取り入れましょう。
おすすめの黒い食材
- 黒豆:腎の働きを高め、むくみを取る。煮豆や黒豆茶に
- 黒ごま:アンチエイジングの代表選手。毎日スプーン1杯を習慣に
- ひじき:ミネラル豊富で血を補い、髪を艶やかに
- 黒きくらげ:血液サラサラ効果と潤い補給
- 昆布・わかめ:腎を養い、体の余分な熱を冷ます
- しいたけ:免疫力アップと気力向上
根菜類で体を芯から温める
冬は地中に育つ根菜類が旬。大地のエネルギーをたっぷり含んだ根菜は、体の芯から温めてくれます。
冬に食べたい根菜
- 大根:消化を助け、気の巡りを良くする
- にんじん:血を補い、目の疲れにも
- ごぼう:腸を整え、体を温める
- れんこん:肺と胃腸を養い、滋養強壮
- かぶ:消化が良く、体を温める
- 山芋・長芋:腎を補い、気力体力を高める最高の食材
「温性」の食材を知ろう
食材には体を温める「温性」、冷やす「寒性」、どちらでもない「平性」があります。冬は意識的に温性の食材を選びましょう。
積極的に摂りたい温性食材
- 羊肉:体を温める力が最も強い。ラム肉のスープは冬の特効薬
- 鶏肉:気を補い、胃腸を温める。手羽元のスープがおすすめ
- エビ:腎を補い、体を温める。背わたを取って丸ごと食べる
- 生姜:血行促進、体の芯から温める。紅茶に入れて
- ニラ:腎を温め、冷えによる腹痛に効果的
- くるみ:腎を補う代表選手。1日3-4個を習慣に
- 栗:腎と脾胃を補い、足腰を強くする
- シナモン:血行促進、冷え性改善。紅茶やカフェラテに
簡単レシピ2品
黒豆とかぼちゃの養生ポタージュ
【材料(4人分)】
- 蒸し黒豆 100g
- かぼちゃ 1/4個(約300g)
- 玉ねぎ 1/2個
- 水または豆乳 400ml
- 塩、こしょう、オリーブオイル
【作り方】
- かぼちゃと玉ねぎを一口大に切り、オリーブオイルで炒める
- 水を加えて柔らかくなるまで煮る
- 黒豆と一緒にミキサーでなめらかにする
- 鍋に戻し、豆乳を加えて温め、塩こしょうで味を調える
- 仕上げに黒ごまを振って完成
体を温め、腎を養い、消化にも優しい冬の万能スープです。
根菜たっぷり養生スープ
【材料(4人分)】
- 大根、にんじん、ごぼう、れんこん 各100g
- 生姜 1片
- 鶏手羽元 4本
- 昆布 5cm角1枚
- 水 1000ml
- 酒 大さじ2
- 塩、醤油
【作り方】
- 根菜は乱切り、生姜は薄切りにする
- 鍋に水、昆布、鶏手羽元を入れて火にかける
- 沸騰したら酒を加え、アクを取りながら弱火で30分煮込む
- 根菜を加えてさらに20分煮込む
- 塩、醤油で味を調える
- 器に盛り、刻んだニラやネギをたっぷり乗せて完成
このスープ一杯で、体の芯から温まり、腎の力も高まります。
冬に控えたい食材と工夫
避けたい食材
- 生野菜のサラダ(温野菜にする)
- 冷たい飲み物(常温か温かいものを)
- 南国のフルーツ(バナナ、マンゴー、パイナップルなど)
- アイスクリーム、冷たいデザート
- 刺身や生もの(加熱調理を基本に)
ただし、完全に避ける必要はありません。
どうしても食べたい時は:
- 生姜やネギなど温める食材と一緒に
- 温かいスープやお茶と一緒に
- 昼間の温かい時間帯に
- 少量を楽しむ程度に
食べるのを我慢ではなく、「体と相談しながら選ぶ」ことが大切です。
まとめ〜立冬から冬至に向けて
立冬を迎え、これから冬至に向けて、陽気はますます少なくなっていきます。
でも、これは自然のリズム。恐れることはありません。
冬を元気に過ごす3つの合言葉
- 温める:ツボ、食事、衣類で体を冷やさない工夫を
- 蓄える:無駄にエネルギーを使わず、腎にしっかり貯金を
- 休む:早く寝て、ゆっくり起きる。頑張りすぎない冬を
今日から始められること
- 湧泉のツボ押しを就寝前の習慣に
- 腎兪か命門にカイロを貼って1日過ごす
- 黒い食材を1品、食卓に加える
- 根菜スープを週に1回作る
- 靴下とレッグウォーマーで足首を守る
冬は「縮こまる季節」ではなく、「充電する季節」。
春に美しい花を咲かせるために、今は根を深く張る時期なのです。
今回ご紹介した冬支度を少しずつ試していただき、体の変化を感じてみてくださいね。
冬は、自分の体と丁寧に向き合う大切な季節。皆さまの冬が、温かく穏やかなものでありますように。
ご質問やご感想がございましたら、いつでもお気軽にお声かけください。
一緒に冬を乗り切りましょう!
またクラスでお待ちしております^^

